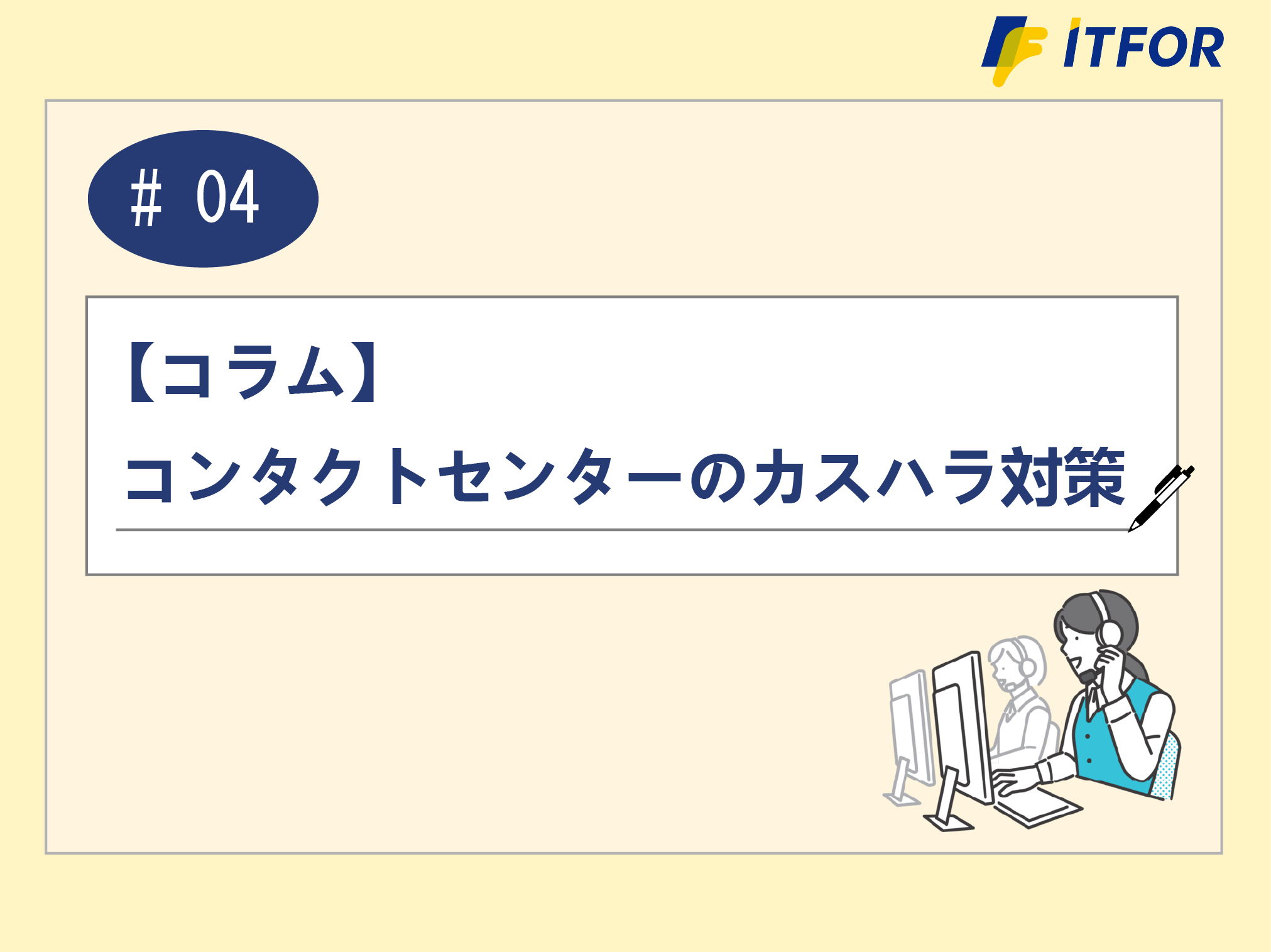カスタマーハラスメント対策は
「人」と「テクノロジー」の力で切り拓く!
前回までのカスタマーハラスメントコラムでは、コンタクトセンターで発生したカスタマーハラスメントについて「人」の力でどう向き合うかを中心にお伝えしてきました。
一方で、近年注目されているのが、AIやシステムなどの「テクノロジー」を活用した対策です。
本コラムでは、「人」と「テクノロジー」それぞれの力に目を向けながら、これからのカスタマーハラスメント対策の可能性を紐解いていきます。
テクノロジーによる対策とは?
前回までのカスタマーハラスメントコラムでもお伝えしてきたように、カスタマーハラスメント(カスハラ)は、オペレーター個人の力だけで対応しきれるものではありません。
コンタクトセンター事業者として従業員の保護に努めていても、現場でその対策を徹底し続けるには、どうしても限界があるのが現実です。
こうした背景から、近年ではAIやシステムといった「テクノロジー」の力を活用したカスタマーハラスメント対策へのサポートに注目が集まっています。
実際に導入が進んでいる機能には、たとえば次のようなものがあります。
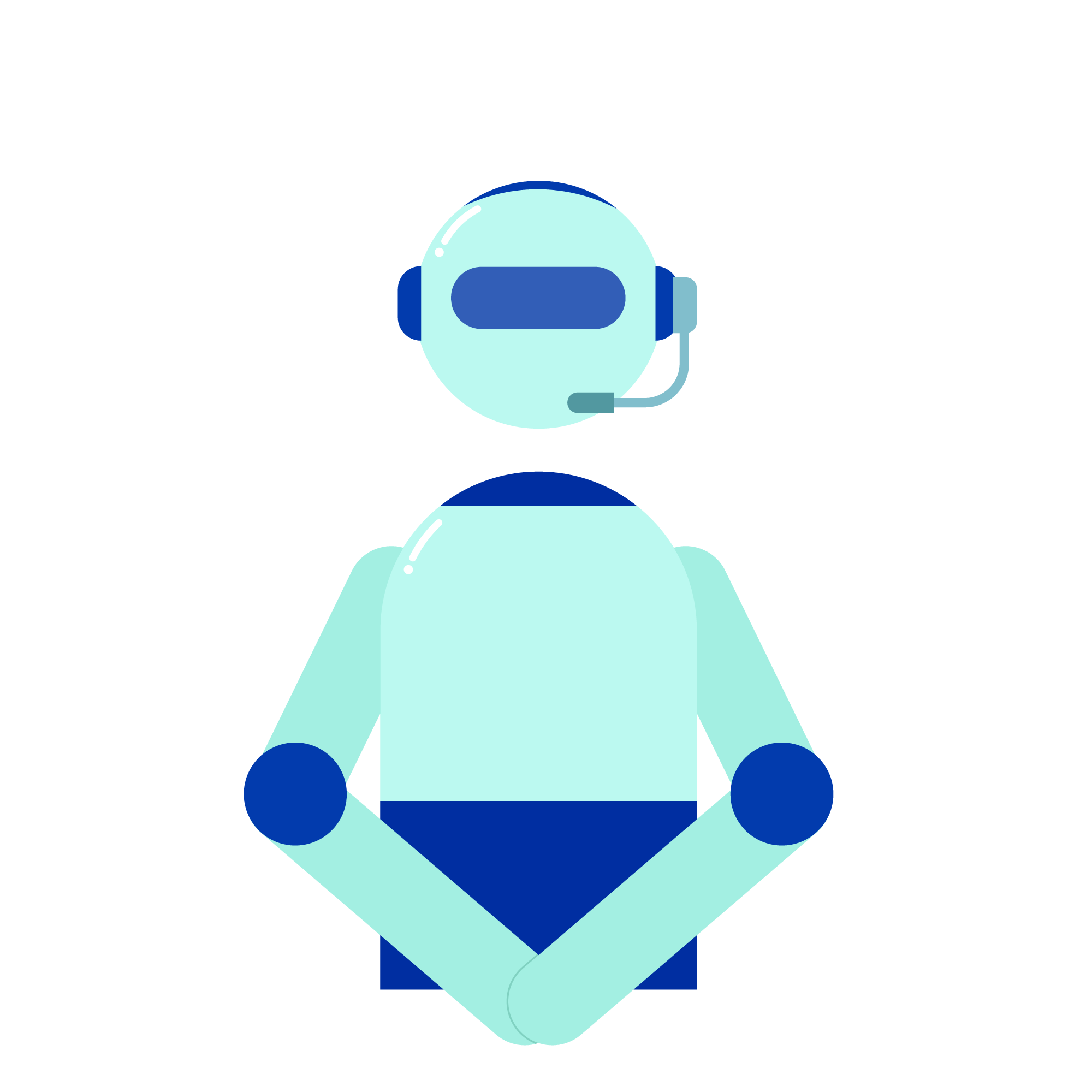
通話中のリアルタイム検知
通話中の検知の方法は大きく分けて、「テキスト」と「音声(声)」の2種類があります。
テキストによる検知では、通話内容をAIがその場で文字起こしし、不適切な言葉やNGワードを即座に検出します。
音声による検知では、相手の声のトーンや話し方から感情を分析し、怒りやイライラなどのネガティブな感情を察知します。
さらに、こうした検知とあわせて、AIが適切な対応例や回答案を提示したり、必要に応じて落ち着いたトーンで自動応答を行ったりするものも登場しています。
カスタマーハラスメントが発生した際も、これらによってオペレーターは冷静かつ適切にその場を収束させるための支援を受けることができます。
通話後の内容整理
テクノロジーを活用したカスタマーハラスメント対策は、通話中のリアルタイムな検知だけにとどまりません。
通話終了後の内容整理や記録の自動化にも大きな力を発揮しています。
例えば、通話内容をリアルタイムでテキスト化した上で、その要点をAIが自動的に要約することができます。
こうした記録は、実際にカスタマーハラスメントが発生した際の証拠として有効なだけでなく、再発防止に向けた事例分析や、事業者としての対応基準の明確化にも役立ちます。
さらに、発生頻度や時間帯、怒りを誘発しやすい内容などを可視化するフィードバック機能により、カスタマーハラスメントが起こりやすい要因を特定し、根本的な対策につなげることも可能です。
カスタマーハラスメントの定義や受け取り方は人によって異なり、現場で一貫した判断を下すのは簡単ではありません。
だからこそ、AIによる客観的な記録と、システム上での基準の明文化は、オペレーターが安心して対応できる環境づくりに大きく役立つ要素となっています。
顧客分析による次回からの対策
カスタマーハラスメントは一度対応して終わりではなく、継続的なリスクとして捉える必要があります。
その点でも、システムを活用した「顧客ごとの記録と分析」は、大きな力を発揮します。
通話中にカスタマーハラスメント行為が検知された場合、その記録はシステム上に保存され、次回以降の対応に活かすことが可能です。
例えば、過去に問題行為のあった顧客から着信があった際に、自動でアラートを表示するなどがあります。
これにより、あらかじめサポート体制を強化したり、事前に管理者が対応にあたるといった対策を講じたりすることができ、オペレーターの負担を軽減する効果も期待されます。
管理者のモニタリングサポート
テクノロジーは、オペレーター自身を支援するだけでなく、彼らを守るための体制づくりにも活用することができます。
例えば、AIが通話内容を即時にテキスト化し、カスタマーハラスメントの兆候を検知すると、自動的に管理者へアラートを送信。
管理者はその通知をもとに、迅速に現場の状況を把握し、適切なフォローを行うことができます。
さらに、AIが通話内容を整理・要約して管理者に引き継ぐ機能もあり、複雑な対応が必要なケースでもスムーズなエスカレーションが可能です。
このように、システムによるリアルタイムの可視化と連携によって、管理側が随時サポートに入れる体制を整えることで、オペレーターの負担を軽減し、より安心して業務に臨むことができるようになります。
なぜテクノロジーだけではだめなのか?
テクノロジーは、現場の負担を軽減し、オペレーターを支える強力な味方です。
しかし、だからといって「すべてをテクノロジーに任せればよい」というわけではありません。
むしろ、テクノロジーには明確な限界があり、それを理解したうえで活用することが、健全な運用には欠かせません。
では、なぜテクノロジーだけでの運用は難しいのでしょうか?
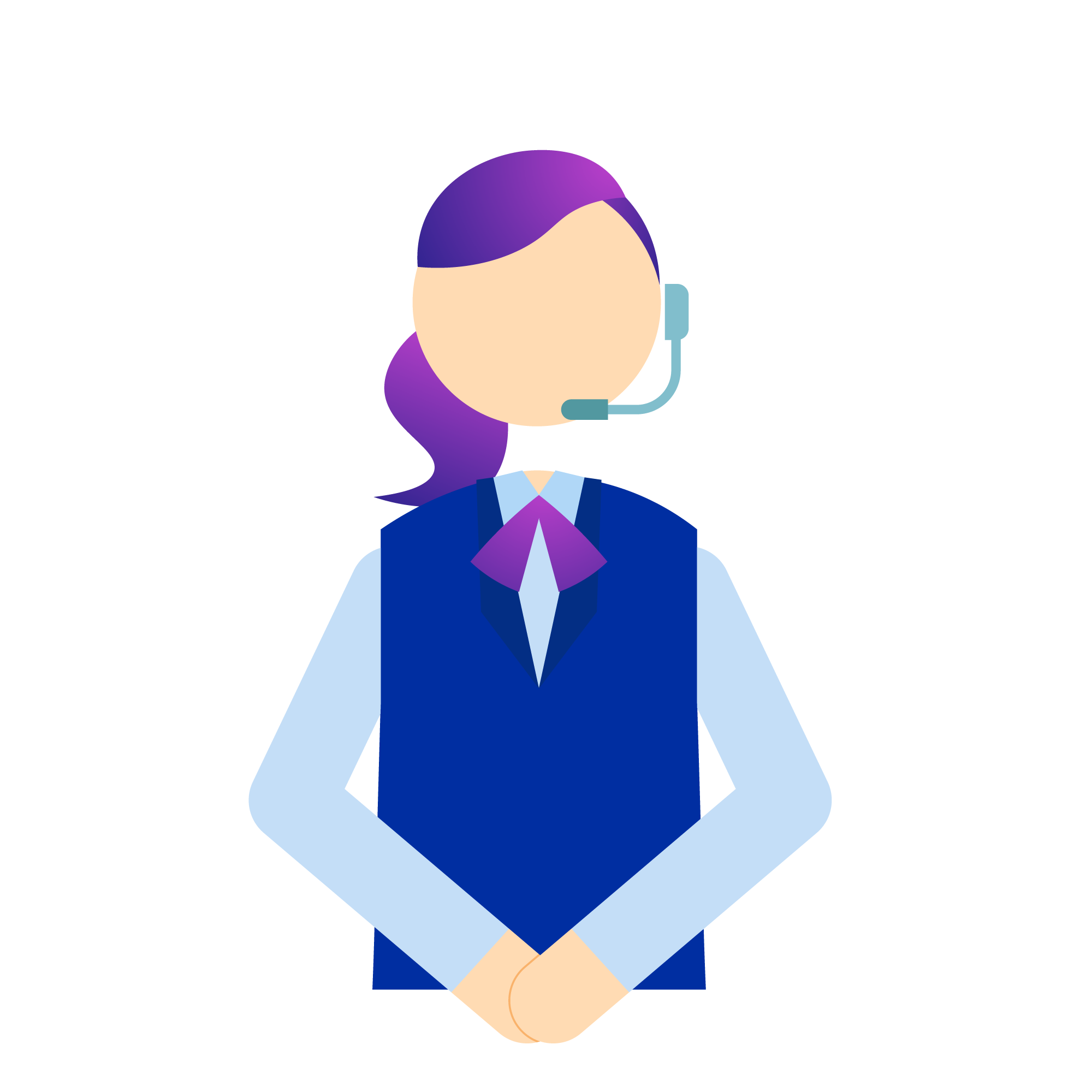
カスタマーハラスメントとなる「基準」の判別
本コラムの前章では、「システムはカスタマーハラスメントの基準を明確化するのに役立つ」と述べました。
AIは「ばか」「ふざけるな」など、明確なNGワードを検知することは可能です。
しかし、カスタマーハラスメントに該当するかどうかの判断は、言葉の選び方や文脈、声のトーン、相手の意図など、複雑な要素が絡みます。
例えば、「こんなサービスでお金を取るなんて…」という言葉が、単なる不満なのか、攻撃的な言動なのかの判断は、文面だけでは難しいものです。
また、自動応答においても、AIがいくつかの提案を出すことはできても、「相手の感情をくみ取り、最も適切な言葉で応じる」といった対応は、依然として人間の感覚に頼らざるを得ない部分です。
こうした「曖昧さ」や「人の受け取り方に左右される部分」こそが、テクノロジーの限界であり、人の判断が必要とされる場面なのです。
プライバシーやセキュリティの懸念
もうひとつ見逃せないのが、プライバシーやセキュリティの問題です。
カスタマーハラスメントの検知や通話記録の保存は、便利な反面、情報漏洩のリスクとも常に隣り合わせです。
例えば、過去に問題のあった顧客の情報が適切に管理されていなかった場合、それを見た担当者が感情的に扱ってしまい、情報漏洩などにつながる恐れもゼロではありません。
こうしたリスクを最小限に抑えるには、セキュリティ基盤の整備だけでなく、体制の整備や、情報の扱いに関する教育といった対策も不可欠です。
また、事前にプライバシーポリシーを明示し、お客様に同意を得ておくことも、信頼関係を築く上で重要なポイントになります。
「人×テクノロジー」の連携が生む、カスタマーハラスメント対策
カスタマーハラスメントへの対策において、人の力とテクノロジーの力はそれぞれ異なる役割を持っています。
テクノロジーは、通話のリアルタイム分析やデータの蓄積・傾向把握といった「広範な処理」や「パターン化された判断」が得意です。
一方で、人はその場の空気や相手のニュアンスに応じた「柔軟な判断」や「共感的な対応」が可能です。
テクノロジーによる分析や提案をうまく活用しつつ、最終的な判断や対応を人の手で行う──
このように、人とテクノロジーが補い合いながら対応・対策をしていくことが、現場にナレッジを蓄積し、継続的な改善へとつなげていく鍵となるでしょう。
以下は、対応フェーズごとに人の役割とテクノロジーの役割を整理した一例です。
通話状況
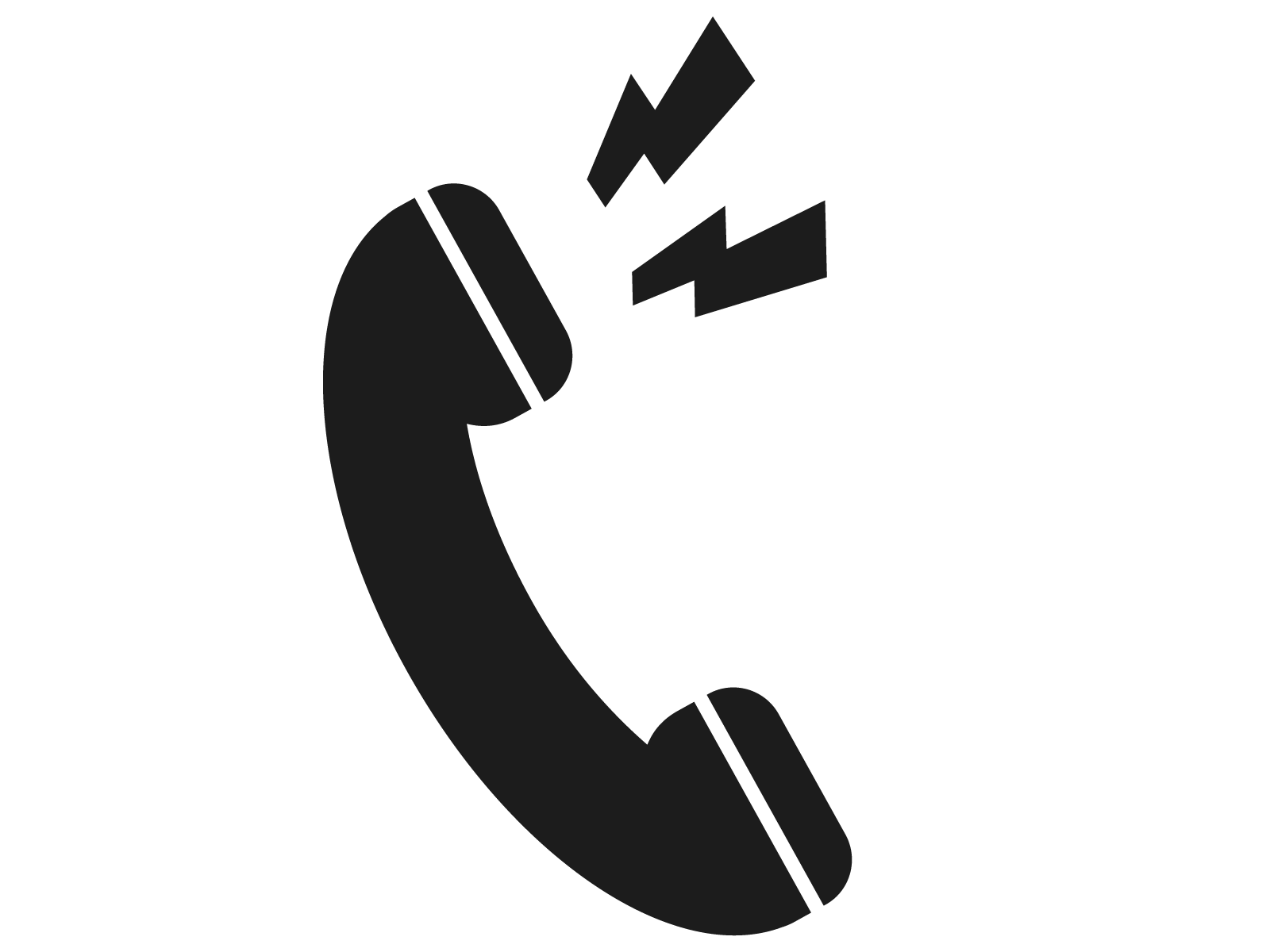
|
テクノロジーの役割
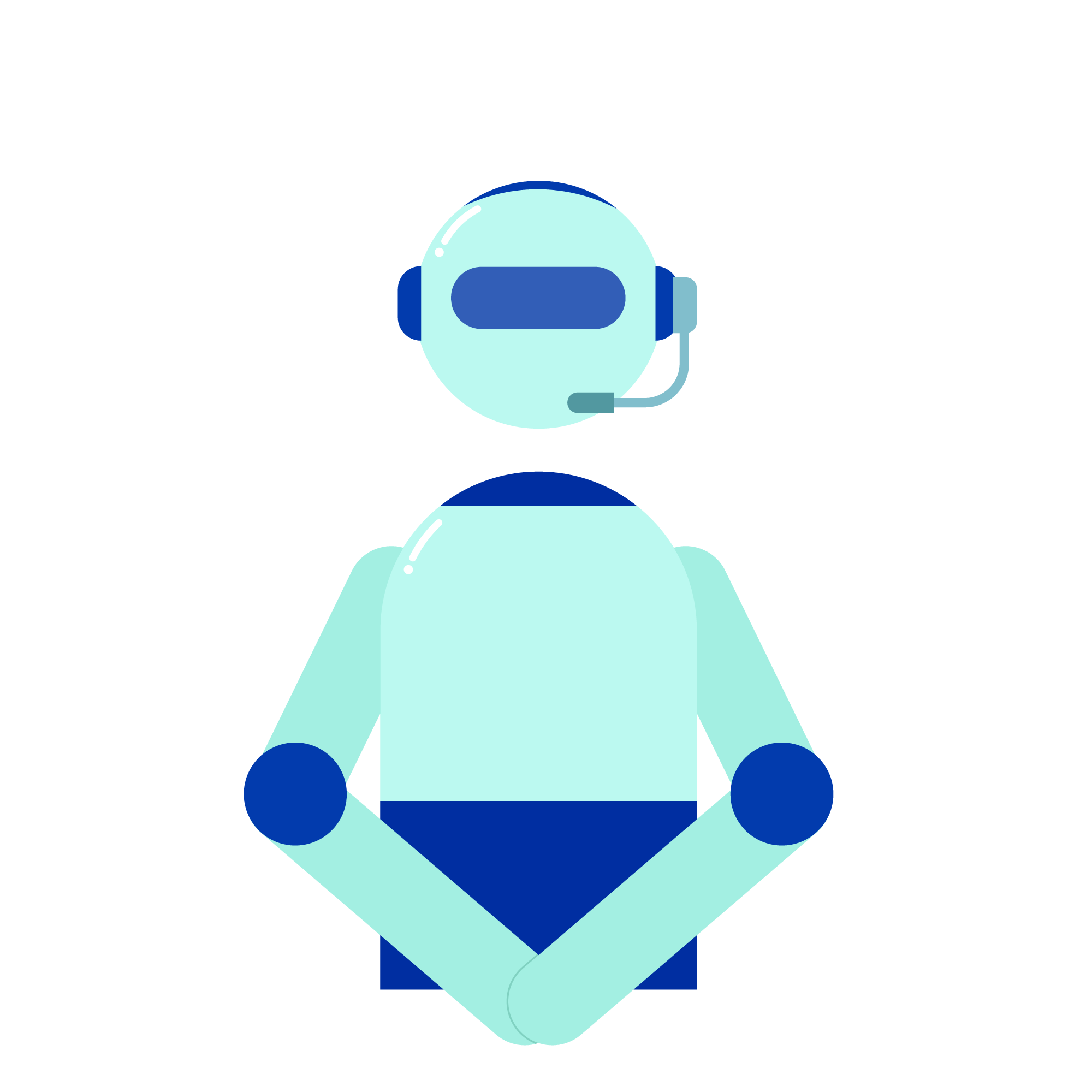
|
人の役割
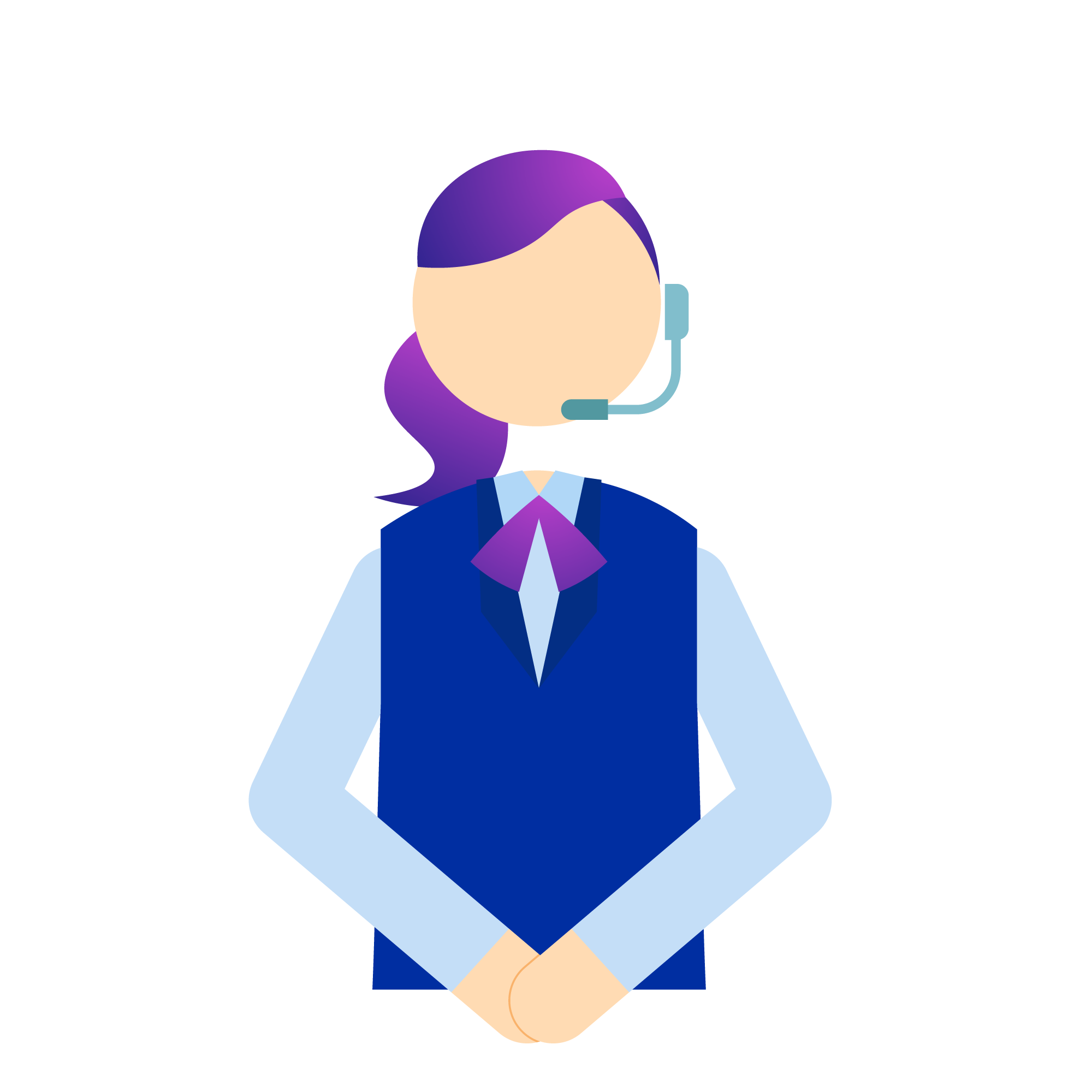
|
|---|---|---|
| 通話中 |
|
|
| 通話後 |
|
|
| 2回目以降の通話 |
|
|
このように、それぞれの得意分野を活かした「ハイブリッドな対策」が、より継続的かつ実効性のあるカスタマーハラスメント対策を可能にします。
まとめ
カスタマーハラスメント対策は、終わりのない挑戦ともいえます。
「人」の感性と「テクノロジー」の客観的なサポートを融合し、現場の経験を積み重ねることで、より良い環境を築いていくことができます。
テクノロジーの力を味方にすれば、対応力が高まり、安心できる職場づくりを一歩ずつ進められるでしょう。
その積み重ねが、コンタクトセンター全体の活力となるはずです。
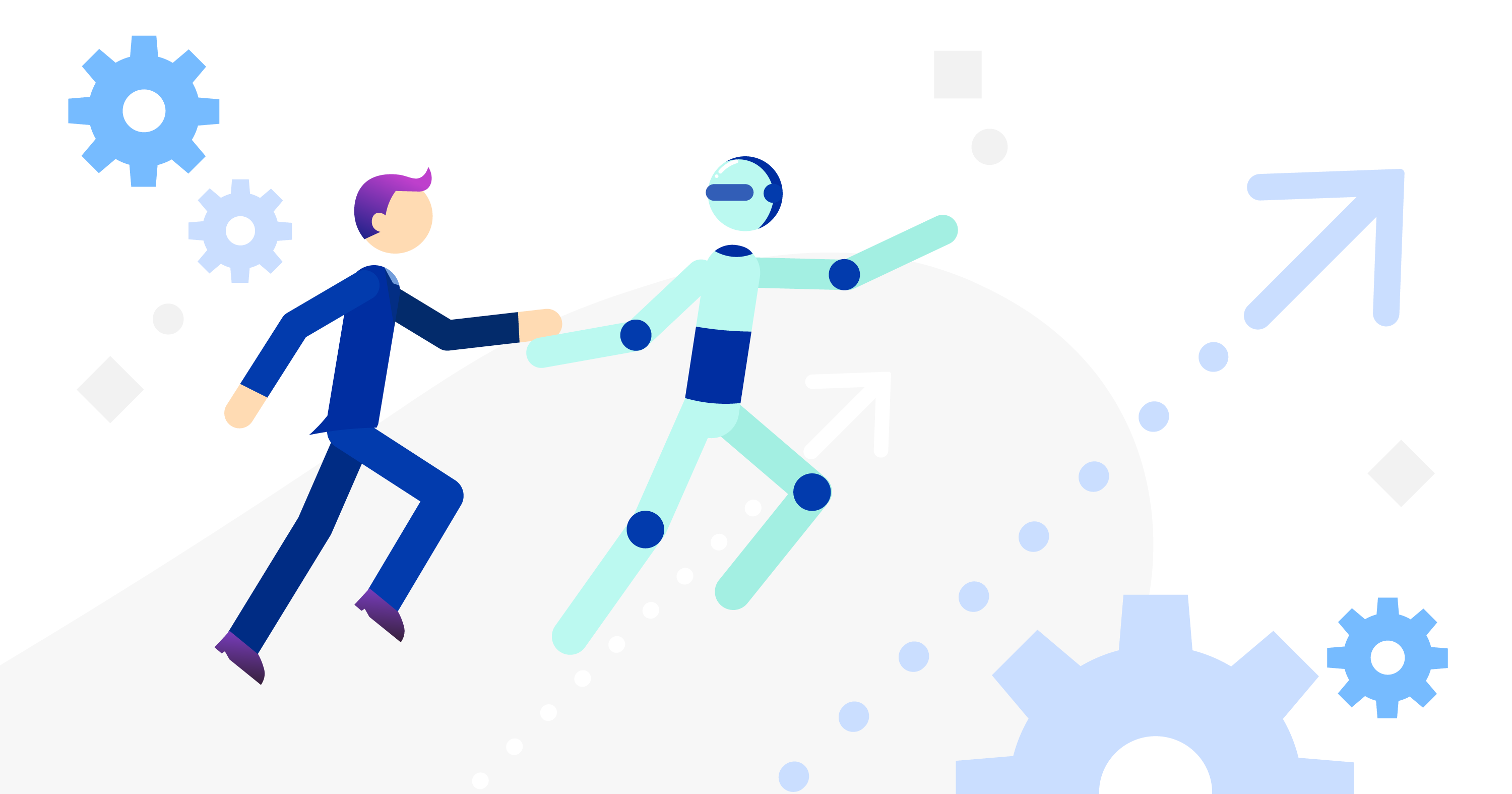
関連記事
現場で即使える!コンタクトセンターにおけるカスタマーハラスメント対応:具体的な切り返しと事後のケア
オペレーターがカスタマーハラスメントに遭遇した際に、どのように対応すれば良いのか、具体的なセリフ例と受け答え、そしてその後のケアについて解説します。