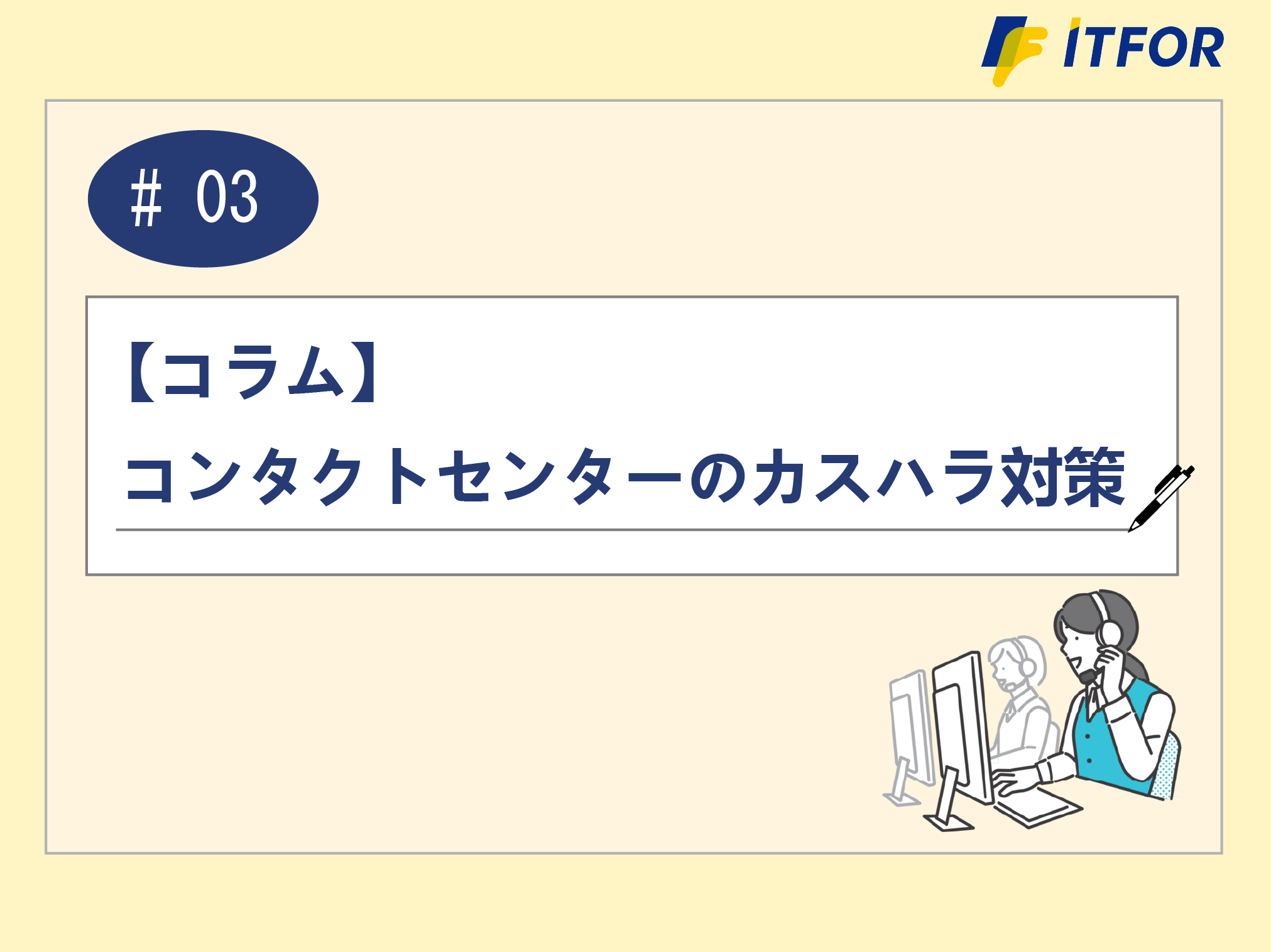あなたの会社は大丈夫?東京都カスタマー・ハラスメント防止条例、知らないでは済まされない
近年のSNSの普及によって顧客側の発信力が増大し、カスタマーハラスメント、通称カスハラが顕在化してきました。そのような中で東京都は、顧客からの迷惑行為や不当な要求を防止し、従業員の職場環境を守ることを目的として、全国で初めて「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を制定しました。この条例は2024年10月4日に全会一致で可決・成立し、2025年4月1日から施行されます。
そもそもカスタマーハラスメント(カスハラ)とは?
カスタマーハラスメントの定義
法律上の明確な定義はまだありません。しかし、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や、東京都の条例などにおける定義から、カスハラは正当なクレームとは異なり、根拠のない言いがかり、過剰な要求、人格否定など、社会通念上不相当な要素を含むことがわかります。
カスタマーハラスメントの具体例
- 従業員への暴言や脅迫
- 長時間にわたる拘束や執拗なクレーム
- 土下座の要求やSNSでの誹謗中傷
- 過剰な謝罪要求やプライベートへの干渉
カスタマーハラスメント対策、待ったなし!東京都の条例が企業に求めるもの
条例の目的
- 従業員が安心して働ける職場環境の整備
- 社会全体でのカスタマーハラスメント防止意識の向上
条例のポイント
対象となる事業者:
東京都内のすべての事業者。飲食店、小売業、医療機関、公共交通機関など、顧客対応を行う業種全般が含まれます。
事業者の責務:
条例の施行に伴い、研修や相談窓口の整備などの対策に加え、カスハラ防止に関するガイドラインの策定など、より広範囲での取り組みが義務付けられます。
顧客等の権利への配慮:
正当なクレームや合理的な要求まで委縮しないよう、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意することも定められています。
もし違反するとどうなる?
条例に罰則規定は設けられておらず、あくまでカスタマーハラスメント行為の抑止効果を期待するものです。事業者への指導や助言を通じて改善を促す形となっています。
ただし、カスタマーハラスメント行為そのものが刑法上の罪に該当する場合は、傷害罪や名誉棄損罪などの法的責任が問われる可能性があります。事業者と従業員の双方がこの点を十分に認識し、悪質な事例については警察や法的機関を交えた対応を適切に行うことが重要とされています。
まとめ:カスハラから従業員を守り、健全な職場環境を実現するために
本記事では、近年深刻化しているカスタマーハラスメント(カスハラ)について、その定義、具体例、そして東京都の防止条例について解説しました。
- カスタマーハラスメントは、従業員の人格を否定したり、脅迫したりする行為であり、許されない。
- 東京都の条例は、カスタマーハラスメント防止のために、事業者にさまざまな対策を義務付けている。
- 事業者と従業員が協力し、カスタマーハラスメントに対する意識を高め、適切な対応を行うことが重要。
東京都に限らず、企業は従業員が安心して働ける環境を整備するために、カスタマーハラスメント対策を講じることが求められます。
関連記事
コンタクトセンター従業員を守るために、今企業ができることは?
カスタマーハラスメントは、もはや個人の努力で乗り越えられる問題ではなくなっています。コンタクトセンター事業者の皆さんがカスタマーハラスメントにどのように向き合い、どのような対策を講じると良いかについて、厚生労働省、東京都の指針を例に解説します。