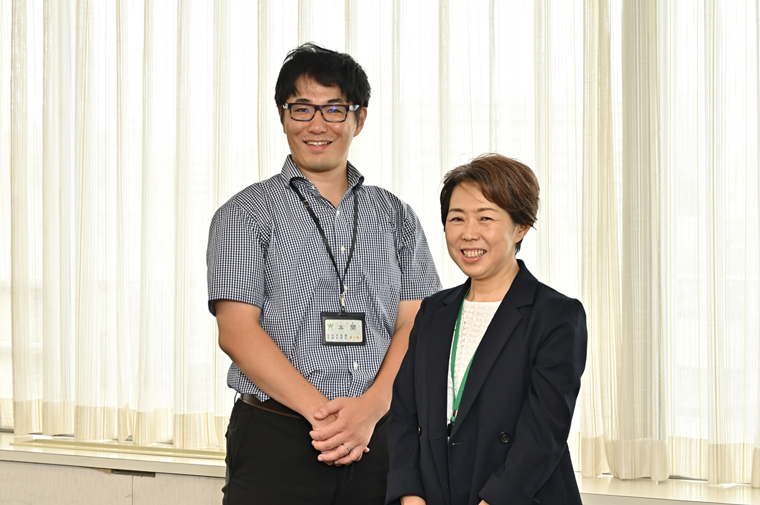自治体向けBPOサービス
【導入事例】荒川区様
国民健康保険料は23区中5位となる約93%の収納率を達成
懸案だった外国人世帯の滞納削減にも貢献中
早くから庁舎内に納付案内センターを設置し、催告業務の民間委託を展開している荒川区。表面化してきた運用課題の解消、懸案だった外国人の滞納率の削減を目指し、2022年4月からアイティフォーのBPOサービス(※)を運用中です。経緯や現在の状況について、契約課を代表して国保年金課に話を伺いました。
- 瀬沼智子 氏 :荒川区 福祉部 国保年金課長
- 本間光祐 氏 :荒川区 福祉部 国保年金課 保険料係長

(※)BPO事業は現在、子会社アイティフォー・ベックスが承継し、運用しています。
滞納発生、長期化抑制に民間事業者のノウハウを活用
東京都23区の東北部に位置する荒川区。JR、東京メトロに加え、京成線や都電が走る鉄道の交通基盤を活かし、かねてより駅周辺や商業地域の再開発を推進してきました。以後これまで人口は増加傾向にあり、2024年8月時点での人口はおよそ22万2000人となっています。外国籍住民も増え全体の約10%を占めており、地域の多国籍化も進んでいます。
そうしたなか荒川区では、各種債権の滞納発生や長期化の抑制に向け、庁舎内に納付案内センターを設置し運用しています。10年以上前に運用を開始、早くから催告業務の民間委託に踏み切り、システム化を含め民間事業者のノウハウを活用し、業務の効率化を図られてきました。
納付案内センターの設置以降、荒川区において現時点で対象となっている債権は、以下のように複数の部署にまたがっています。
- 国保年金課:国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、保険給付返還金
- 税務課:特別区民税・都民税・森林環境税、軽自動車税
- 介護保険課:介護保険料
- 児童青少年課:学童クラブ保育料
- 保育課:保育園保育料
表面化した課題の解消が収納率の上昇につながる

現在国民健康保険料の催告業務を担当するのは、福祉部 国保年金課 課長の瀬沼智子氏と同課 保険料係長の本間光祐氏。国保年金課では、国民健康保険、後期高齢者医療制度等に関する加入・脱退や給付、また国民年金も管轄。保険料の収納管理や滞納整理、支払いに関しての相談窓口といった役割も担っています。業務課題に対してはIT化にも取り組み、収納チャネルの拡大、申請手続きのオンライン化など整備しており、業務効率や住民サービスの向上につなげています。
催告業務について「収納率は年々向上しています」(瀬沼氏)というように、納付案内センターの運用はしっかりと機能してきました。特にここ数年は高い上昇率を示し、「現年分の収納率は平成30年度の88.72%から令和5年度の92.73%と、5年間で4.01ポイント上昇しています。92.73%は、23区内で5番目の収納率になります」(瀬沼氏)。それまでは順位も10番目以下で、80%台の収納率を推移しており、短期間で劇的な改善が図れたことになります。また、滞納繰越分の収納率も同期間で10ポイント以上の上昇につながったと言います。
その背景には、納付案内センターの運用で表面化してきた課題への対策が大きな要素となっています。当時の状況について瀬沼氏は「それまでの催告業務は架電と訪問が主でした。毎月の同日、同時間帯に滞納者と接触を試みて、会えなくても同じ対応を繰り返すことが多く、成果につながる兆しが見えづらい状況でした」と話します。
また荒川区にとっての大きな課題が、多国籍化が進む外国人被保険者の対応。現在では、国保加入世者の約20%が外国人と言います。「もともと文化の違いから、どうやって制度の理解を図るか、交渉していくかといったことに苦慮していました。催告業務も電話による接触回数や訪問件数自体は順調に推移しているものの成果と比例せず、その接触実績が収納にどう結びついたのか検証しづらい点もありました」(瀬沼氏)

プロポーザル方式で課題解決に向けた提案を公募

そうした状況にあって、2022年3月の契約者との履行期間終了にともない事業者からの提案を公募。複数の提案のなかから、当社が展開する債権管理ソリューションであるBPOサービスを採用いただきました。BPOサービスは、催告業務効率を最大化するシステム環境と、専門的な教育・研修を受けた専任スタッフをトータルに提供するものです。同区が選定手法としたのはプロポーザル方式(提案評価方式)。本間氏は「こちらの要求に対し、どう理解しどのような内容で運用する考えなのか、コストによらず各社の考えをきちんと見極めたいということでプロポーザル方式を採用しました」と話します。
ニーズに見合った業務システムと架電、訪問、事務補助業務等を担当するスタッフを配し、2022年4月から納付案内センターの運用を開始しました。大きな課題である外国人対策には、中国・ベトナム・ミャンマー・ネパールなど母国語で対応できるスタッフを揃え、スムーズにコミュニケーションできる体制を整えました。また催告業務以外でも、区役所を訪れた住民を速やかに誘導するフロアマネージャーも手配し、住民サービス向上の一端を担っています。
BPOサービスの催告業務システムからはSMS(ショートメッセージサービス)送信システムが採用されました。“電話に出てもらえない”“封書が開封されない”といった、どの自治体も悩まされる課題があります。そうしたなか、滞納者の携帯電話にダイレクトにメッセージを届けるSMSは高い視認率が期待されます。「SMS送信システムは、提示した提案限度額の範囲内で提供可能という提案をいただき、それならぜひにとお願いしました」(本間氏)。
いつも持ち歩いている携帯電話に宛てるメッセージは、気づいてもらいやすく、常に確認できる状態にあるため高い開封率が見込めるもの。とはいえ、そうした効果を享受するには工夫も必要です。瀬沼氏は「比較的少額の滞納者に未納のお知らせを送信していますが、高額滞納者、外国人も対象に、毎月のように配信対象を変えて既読スルーを防ぐようにしています。外国人には英語等、その人に伝わりやすいメッセージにして送信しています」と話します。
こうした“催告慣れ”は、どの方法でも起こりえるもの。同課では架電や訪問による催告も対象ごとに切り替えて展開していると言います。「催告の基本はあくまで架電や訪問で、直接コミュニケーションさせていただくことと考えています。ただ毎回電話や訪問ばかりで“またか”と慣れが生じてしまうことを避ける意味でも、今月はあえてショートメールを送ってみようとか、文書を送ってみようといった工夫をしています」(本間氏)。

母国語でコミュニケーションできるスタッフが存在感発揮
「外国人の被保険者による滞納は着実に減少しています」(瀬沼氏)ということで、母国語でコミュニケーションできるスタッフの貢献も大きいと言えます。保険制度の知識を備えた職員同然に、単に通訳にとどまらない対応が成果につながっているようです。
「知識を持って同じ国の人として会話していただけるので、的確に意味が伝わっているのだろうと感じています。例えば、保険料を支払うことで病院での負担が少なくなるということでも、通常の通訳だと“ディスカウントカードがもらえる”といった伝わり方で終わるところが、きちんと保険制度として理解につながるように伝えていただけていると思っています。カウンターの外側ではなく内側にいて職員サイドで対応していただける存在です」と瀬沼氏は言います。


通訳としての対応業務時間は、年間延べ約596時間(令和5年度実績)。端末越しに通訳オペレータと対話するライブ通訳サービスの利用料(330円/分)に換算すると、約1,180万7,000円に上ります。こうした費用対効果の面からも、通訳スタッフの効果の大きさがうかがえます。
「ベトナム語やネパール語までも網羅できるのはありがたいです。職員が行う翻訳作業も依頼しますし、かなり効果的に活かされていると思っています」(瀬沼氏)。
また、本間氏は「外国籍の方はその国の性格があるので、その認識のもとに“こうすると制度への理解が進む、収納がはかどる”といったことを共有して、対策を一緒に考えていけたらいいのかなと思います」とさらなる期待を口にします。
滞納の未然防止に取り組み収納率向上を目指す
「いままで数名の職員が専任で対応していた財産調査なども納付案内センターで対応いただいています。その分、滞納整理に注力できるなどの好循環も生まれていて、こうしたことも成果につながっているものと思います」(本間氏)
こうして催告業務の民間委託によって生まれた好循環を今後も活かし、大きなテーマとなる滞納の未然防止に取り組んでいく考えです。
「滞納者の対策ということでは、われわれが思いつく内容は出し尽くした印象があります。他自治体様の好事例を共有いただくなどして、口座登録の獲得率の向上も強化していければと思っています」(本間氏)、「外国人に限りませんが、特に外国の人は日本のような保険制度は未経験ですから、制度の理解を促進できればと思っています。例えば日本語学校に対して説明するなど滞納の未然防止に取り組み、収納率の向上を図りたいと思います」(瀬沼氏)と語っていただきました。